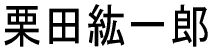
C組出身の栗田紘一郎(栗田紘一)君を応援しよう!
<略歴>
関西学院大学で視覚心理学を専攻、カメラを用いて視覚実験を行い写真と本格的に関わる。
1966年 関西学院大学卒業。
1967年 東京で広告代理店に所属し、広告写真をはじめる。
1983年 ファインアーツフォトに転向、専念するために八ヶ岳に暗室とスタジオを建て
8×10インチ用
水平移動型引伸機を設置。風景写真の制作を始める。
1993年 アーティストとしての永住権を得てニューヨークに住む。ウィトキン ギャラリー(NY)と契約、
1995年東京、パリ、ニューヨークで個展が開催される。
1996年 ニューヨーク SOHOにスタジオと暗室を設け、本格的に作品制作を開始、ラージサイズの
プラティナプリントを始める。
2000年 ラージサイズプラティナプリントのエキジビションが6ヶ月間、ニューヨークとサンフランシスコ
のギャラリーで開催され、ニューヨーク展がニューヨークタイムスにもとりあげられる。
2001年 スタジオをNYチェルシー地区に移す。写真ワークショップとギャラリースペースを設け、後進
の指導に当たっている。
作品は日・米・欧の主要ミュージアムに所蔵されている。

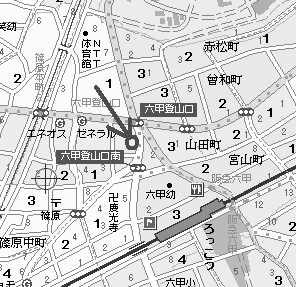
開催期間:4月10日(日)〜24日(日)
時間:am11時からpm6時 (水曜定休)
場所:神戸市灘区篠原本町1丁目7-25
「Gallery Kobeきたむら」
電話 078-881-3030
(栗田君本人は、登場しません。)
※詳細は開催責任者、長井君(G)にお問い合わせください。
<プラティナプリントについて>
ブラック&ホワイトのフォトグラフと言えば 一般的にはゼラチィン シルバープリントを指しますが、 実際には様々な異なる技法があり、 同じオリジナルネガから作る事ができるということで、 それらをオルタナティブ・プロセスと呼んでいます。
代表的な技法としてはCalotype, Cyanotype, Kalitype, Alubumen, Platinum/Palladium print, Gum Bichromate, Carbon printなどが挙げられます。 その中でもfinest monochrome printing processと考えられているのが プラチィナ・パラデューム・プリントです。
プラチィナ・パラディウムプリントの歴史は古く現在のゼラチィンシルバープリント以前に 盛んにプリントされた技法で当時1900年の初めにはコダックを始め多くのメーカーから 印画紙が供給されていましたが現在はありません。
従ってプラチィナ・パラディウムプリントを作る為には自分で印画紙を作ることから 始めなくてはなりません。 プラチィナ・パラディウムプリントはゼラチィンプリントのハロゲン銀塩の感光とは 本質的に異なり、化学的にはFerric Oxalate(蓚酸第二鉄)の感光性と還元性を利用した物で、 Ferric Oxalate溶液に塩化プラチナや塩化パラディウムを加えた液を湿布した紙に光を与えると Ferric Oxalateが感光し、還元された蓚酸第二鉄は放失した酸素の代わりに光の量に応じて プラチィナ及びパラディウム金属を取り込み、黒化した濃淡を作るという性質を利用したもの と解説されています。
プラチィナやシアノタイプなど多くのオルタナティウ゛・プロセスでは 感光材料の感度が低く、紫外線にのみ感光するという性質から、 エンラージャーを使っての拡大プリントが出来ません。 プリント作業は長時間の密着プリントになります。 言い換えればプリントと同じ大きさのネガを作る必要があります。 オリジナルの小さなサイズのネガから自由な大きさのプリントが引き延ばせる ゼラチンプリントと大きく異なる点はここに有ります。 大きなサイズのプリントを作りたい場合はそのサイズのカメラを使用するか 引き伸ばして拡大したネガを作るかのいずれかになります。
この様に大変な手間をかけたプラチィナ・パラディウム・プリントは 柔らかな暖かい感じ、豊かな階調域、そして立体感など優雅な特徴を持っています。 また安定性の良い経年変化のないプリントとも言われており、 ファインアート・フォトグラフの中では別格の地位を得ています。
[先頭に戻る]