|
石原莞爾選集(全10巻)合本版
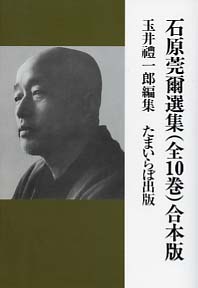
石原莞爾著 玉井禮一郎編
2002年03月01日 第2刷発行 税込価格 \36,750
A4判 並製 850頁 ISBN4-88636-063-7 C0395
|
編者のはしがき
「石原は、戦後も、世界最終戦の切迫と非武装中立を国民に訴えたが、彼の最終戦の回避と非武装中立の可能性の保障こそ、西欧的覇道とはちがった価値観に立つ東洋的王道にもとづく新しい東亜連盟の結成だったのである。ここに私たちの近未来における選択の一つの方向が示唆されているといってもよい」
これは『石原莞爾(甦える戦略家の肖像)」(現代書林)の著者佐治芳彦氏の言です。
また『石原莞爾資料、国防論策篇』(原書房)の編者角田順氏は、同書のなかで、
「昭和の陸軍の歩みを考察するに当っては、よかれあしかれ石原莞爾の存在を度外視する訳には行かぬであろう」と述べています。
「皇軍」すなわち国家だった昭和前期を論ずる場合、この角田順氏の述懐のなかの「陸軍」を「日本」と置き換えることもできるでしょう。
没後三十数年、石原莞爾に関して出版・公刊された伝記・論文のたぐいは三百篇にものぼるといわれていますが、一軍人の事績がこれほど多くの人から論じられることは類例がありません。
その内容は「天才的軍略家」「予言者」「満州事変にはじまる十五年戦争の点火者」等毀誉褒貶かまびすしいものがありますが、いまだに万人がうなづける評価が定着しているとはいいがたい観があります。もちろん、いかなる歴史的人物にせよ、万人を納得せしめる評価を下すことはむずかしいことかもしれません。石原莞爾の場合は、その内面とくに信仰面について語られたものが少ないことも、彼を正しく評価することを阻む大きな理由の一つであり、その解明が急がれます。
さいわい、この書簡集と同時に小社から発行される「石原莞爾(「永久平和」の先駆者)」(入江辰雄著)は、
同じ著者による「石原莞爾と伊地知則彦」(武田平和研究所)、「日蓮聖人と石原莞爾』(たまいらぼ)とともに、日蓮教徒としての石原莞爾の実像に迫る労作であり、その解明はすでになされつつあります。
ところで人間はある日突然回心・発心するものではなく、信仰に入ってからも、発展ないしは転回(または転向)という変化をするもので、石原莞爾研究者の一人として私がとくに関心をもつのは、石原莞爾の信仰のプロセスおよびそれにもとづく思想形成の過程です。その点の充分な解明がなければ、石原莞爾という昭和史に屹立する巨人の全人格的解明もされないでしょう。
石原莞爾自身はその信仰について、晩年の著作『日蓮教入門』や『日蓮聖人伝覚え書』以外にあまり多くを語っていません。
《……猛訓練によって養われて来たものは兵に対する敬愛の念であり、心を悩ますものは、この一身を真に君国に捧げている神の如き兵に、いかにしてその精神の原動力たるべき国体に関する信念感激をたたきこむかであった。(中略)一時は筧博士の『古神道大義』という私にはむずかしい本を熱心に読んだことも記憶にあるが、遂に私は日蓮聖人に到達して真に安心を得、大正九年、漢ロに赴任する前、国柱会の信行員となったのであった。殊に日蓮聖人の「前代未聞の大闘諍一閻浮提に起るべし」は、私の軍事研究に不動の目標を与えたのである。》(『戦争史大観の由来記』)
《昭和二年の晩秋、伊勢神宮に参拝のとき、国威西方に燦然として輝く霊威をうけて帰来、私の最も尊敬する佐伯中佐にお話したところ余り良い顔をされなかったので、こんなことは他言すべきでないと、誰にも語ったこともなく、そのままに秘し置いたのであるが、当時の厳粛な気持は今日もなお私の脳裡に鞏固に焼き着いている。》(同上)
これらの記述は、石原莞爾の確乎たる信仰・信念の一端を示してはいるものの、あまりにも簡略な記述のために、いささかもの足りないのですが、その信仰と信念を知るうえで決定的ともいえる資料が、この書簡集です。
大正九年五月から大正十年一月まで、赴任地である中国の漢口から石原莞爾が新婚間もない錦夫人宛に日記ふうに綴って差出したこれらのおびただしい書簡は、夫人の没後石原家の仏壇のなかから発見されたものであり、大正九年八月二十八日付と九月十日付の二通を除いては、これまで未発表未公刊のもので、そのおびただしい書簡群の存在すら石原門下の数人の人以外は未知のものでした。
書簡の内容は、ほとんど信仰上のことで占められており、公臨をはばかるような内容のものはふくまれていません。ちなみに書簡の原本は山形県酒田市立図書館に収蔵されており、そのコピーは最近になって公開されております。小社では、これらの書簡こそ、石原莞爾の信仰面の真実を知るための第一級の資料と評価し、関係方面の諒解をえて出版に踏みきったものです。
ところで、今なぜ石原莞爾なのか?です。
それは、この文の冒頭に引用した佐治芳彦氏の「私たちの近未来における選択の一つの方向」に関連しますが、日本人が自らのアイデンティティを確立するためには、石原莞爾が主唱し、実践した最終戦争観と永久平和論、そのための方略としての満州建国と東亜連盟運動の検証が必須だと思うからです。佐治芳彦氏は同著の序章で、こう述べています。
《私は、太平洋戦争を、基本的には近代日本の民族的同一性の達成――拡大の挫折としてとらえている。明治維新によって近代国家として発足した日本は、日清・日露戦争を経て、その民族的同一性を確立するのに成功したと見てよいだろう。だが、同一性は拡大を求める。その同一性の拡大は必然的に同一性の混乱――同一性の危機に直面する。(略)さて、民族的同一性とかぎらず、集団的同一性が危機にあるとき、集団内に危機突破のコンセンサスが醸成されてくるが、これが典型的同一性であり、ふつう危機の本質を洞察し、そのコンセンサスをリードする特定の人物の出現となる。私が石原莞爾に注目したのは、私の現代史研究において、石原こそが、太平洋戦争の本質をもっとも深く洞察し、また自身、太平洋戦争にもっとも深くかかわっていた軍人であっただけでなく、彼こそこの典型的同一性とよばれるにふさわしい存在であったことを知ったからである。》
そして、日本は敗戦によって、その自己同一性の危機を突破するのに失敗し、挫折したわけですが、日中戦争に反対し、日米開戦前に予備役に編入された石原莞爾の「典型的同一性」としての真の価値は、ほとんど実証されないままで残された、と視ることもできます。
そこで今や、日米貿易摩擦などに象徴される日本をとりまく国際環境の危機が、期せずして再び「典型的同一性」としての石原莞爾の検証ないしはその戦争観と世界構想の再構築を要請しているのではないでしょうか。
ユダヤ人もアラブ人も、ソ連人もアメリカ人も、それぞれ民族としての自己同一性は鮮明です。フランス人もイギリス人も中国人も、その自己同一性は日本人ほど不透明ではありません。ところが、ひとり日本人のみが、外見こそメガネとカメラで戯画化されるほど個性的であるにもかかわらず、その内面となると、「曰く不可解」ないしはエコノミック・アニマルという評言が出るありさまです。
「八紘一宇」や「大東亜共栄圏」における日本中心主義は勿論是認できないかも知れませんが、日本中心主義を消去した「八紘一宇」や「環太平洋経済共栄圏」は今月も立派に通用する思想であり、石原莞爾の「永久平和」や「東亜連盟」のなかに、その思想は生きています。
とまれ、過ぐる敗戦によってザイン(在る)とゾルレン(在るべき)の乖離が始まった日本および日本人は、その状況をも逆手にとって今日の経済的繁栄を築きあげました。
しかし、現在の日本をとりまく国際環境は、次第にホンネとタテマエの使い分けといった手法による一種の「偽善」や「詭計」を許さない方向に動いているように見えます。それは、好むと好まざるとにかかわらず、世界が総合的に一体化の方向を目ざす歴史的段階に突入していることを実感させられます。
そうした人類史上の大きな結節点に際会するとき、在る日本と在るべき日本との距離を縮めることに渾身の努力を傾注した実践的思想家石原莞爾という人物を、かつてわれわれが持ちえた意味はきわめて大きいと思われます。
石原莞爾が民族協和の総本山として建学した満州建国大学の教授中山優氏は、戦後、その回想記のなかで次のように述べています。
《天才の真の意味は、その存在によって何時でも人々に希望を抱かせることであるかも知れぬ。(略)第一次世界大戦当時、北京の辜鴻銘翁がよく西洋人の記者を捉えては、『あなた方は文明の意味を知っているかね。文明とは自動車や飛行機の数ではないよ。一国文明の高さは、その国の文明が生んだ最高の人物によってきまるものだ』といったものだが、それが今日の我々には痛切に思い出される。何の幸いか、我々は身近く将軍を知り得た。将軍は、日本アルプスの雪線の様に、我々の民族能力の水準の高さを示している。それは又地下の水脈の如く、我々の努力によって無限の文化価値を生み出す可能性を示している。》
最後に、この選集の刊行にあたって、●夫人の実家である国府家の当主、国府康昌氏から寛闊なる諾意をいただき、また、協和会はじめ石原莞爾の遺志を継承される多くの方々からも賛意が得られたことを、感謝とともに記しとどめます。願はくは、この選集が基礎となって、より完全な大全集が発刊されんことを。
昭和六十年六月五日
たまいらぼ主宰 玉井禮一郎
●…金偏に弟
全目次
総目次
石原莞爾選集1 漢口から妻へ
石原莞爾選集2 ベルリンから妻へ
石原莞爾選集3 最終戦争論/戦争史大観
石原莞爾選集4 昭和維新論/マインカンプ批判
石原莞爾選集5 教育革新論/国防政治論
石原莞爾選集6 東亜連盟運動
石原莞爾選集7 新日本の建設
石原莞爾選集8 日蓮聖人伝覚え書
石原莞爾選集9 書簡・日記・年表
石原莞爾選集10 「石原莞爾論」集
索引
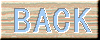
|