|
立正安世論Ⅱ

玉井禮一郎・小牧久時共著
1991年12月8日発行 税込価格 \1,575
A4判 並製 850頁 ISBN4-88636-057-2 C0015
|
目次
序章 ニユーヨーク・タイムズ紙上で(小牧久時)
ライナス・ポーリング博士殿
●『絶対平和への四段階』
第一章 ある創価学会員からの質問)
●ある創価学会員への回答
「付属」が出世の本懐ということがわからない
釈尊も日蓮仏も付属が出世の本懐
本尊は御直筆そのものに限るのか?
三通りに読める「後五百歳之時」
「付属相承なき弘宣は横領・私闘の如し」
「事の一念三千」の「事」は事物の「事」にあらず
大本尊が隠し留められた期間は「無仏」か?
日蓮正宗の本尊は功徳がないか?
第二章 第一回霊山会講話)
苦を抜いて楽を与えるのが仏教
お釈迦さまは日蓮聖人にバトンを渡した
現代にふさわしい仏道修行とは
本尊とはモノなのかココロなのか
本尊は紙でも板でも石でもない
第三章 小牧久時博士からの親書)
「畜生界脱落の本尊」に衝撃
『ことぱ』とは三秘の妙法
湯川秀樹博士夫人にも
小牧博士からの親書
御眷族三名も帰正
京都に一寺建立の誓願
小牧博士から日禮へ
学長就任ごあいさつ
小牧博士から太田竜師へ
日禮から小牧博士へ
小牧博士から日彊へ
日禮から小牧博士へ
第四章 立正安世大宝塔この国に立つ)
●立正安世大宝塔除幕式
●立正安世大宝塔除幕式に臨んで
『立正安世大宝塔』この国に立つ
●現代の法華経とは「南無妙法蓮華経」
●予言の的中こそ宗教の生命
●難信難解の「五五百歳二重」説
●大本尊御讃文こそ最重要の御書
●御讃文の正しい読み方
●「後五百歳之時」の三通りの読み方
●「第三の法門」は御讃文に秘沈
●始めてこれを拓いた者が弘宣すべし
●「事の一念三千」の「事」は「事柄」
●「法華宗」員「妙法蓮華宗」
●地球規模の「三災七難」競起のとき
●地球史の転換期を示す実証
●ノストラダムスの予言も的中か
●過去、現在、未来が同時に存在?
●五百年以上を経てもたらされる啓示
第五章 台湾に一カ寺開かる)
●台光寺の頼日宙師の各方面への弘宣状
●中華民国日蓮正宗仏学会に対して
●台北問答
●台光寺入仏式に臨んで
「広宣流布」は始まったばかり
本門戒壇は、「世界立」であるべき
妙法蓮華宗の後継者は中国の人の中から
台光寺は中国・東南アジアの大本山
第二番御出現の始拓大本尊は台光寺へ
御祝辞
阿部日顕(日蓮正宗法主)師に答える(玉井日禮))
お禮状(小牧久時))
あとがき)
付録「妙法」とは何か?)
あとがき
自分でそうしたいと思ったわけでもないのに、なにか、目に見えない大いなるものに操られるように動かされて、よんどころなくそういう成りゆきに成る、ということがありますが、私は、それが仏といわれるものの存在証明の一つであるような気がします。
さきに『立正安世論Ⅰ』を世に問い、内外から思いがけない高い評価を得た余勢を駆って、『立正安世論Ⅱ』と『立正安世論Ⅲ』を上梓しようとして、まさに印刷所に下版しようとした矢先に、ある読者からの知らせで、日蓮正宗総本山大石寺管長の阿部日顕法主上人が、主として『立正安世論Ⅰ』に対する論難を、宗門の機関誌である『大日蓮』(平成三年十月号)に掲載していることを知りました。
私は、かつて自分も帰属していたことのある日蓮正宗および日蓮門下に対して、数ケ度諫暁書を発表したことがあります。
第一回目は昭和五十五年(一九八〇年)四月二十八日付で、安立行というペソネームで『日蓮大聖人自伝』という書を著わし、日蓮正宗大石寺が日蓮大聖人の御遺命である『三大秘法抄』で御示しの本門の戒壇の条件を忘却して、創価学会の己義による「民衆立」の正本堂を建立したことを批判したものです。このことは、現在の宗門と創価の、修羅と悪竜の闘いにも似た骨がらみの確執の真因をなすものであります。
第二回目は、昭和六十一年三月に、万年救護大本尊の本尊義を認めようとしたい阿部日顕法主と、当時の日蓮正宗総講頭だった池田大作氏の両名に対して、内容証明付きの詰問書を送りました。これに対する返事はいまだに来ませんが、同年四月八日の聖教新聞紙上に、阿部法主が全一ページにわたる反論らしき文章を掲載されていたことが記憶に残っております。しかし、当時は、私が小野寺日了と称する「天一坊」にたぶらかされていた時期で、小野寺の正体に疑問を感じ始めていたときだけに、私は敢えて放置しておきました。また、この時期は始拓大本尊御出現以前であります。
第三回目は昭和六十一年八月二十日発行の『大本尊ふたたび出現す』を著述刊行。しかしこれは小野寺直にたぶらかされかけていたころのもので、後日小野寺の正体が分ってからは絶版処分にしました。しかし、万年救護本尊の御相貌、座配等に対する信解としては、最初の公式発表といえるでしょう。
そして、この法難によって真の信解がひらかれ、領玄寺大宝塔の始拓大本尊御出現となるのですが、第四回目としては、昭和六十三年十一月二十五日『創価学会の悲劇』を公刊しました。
第五回目としては、平成元年四月二十八日『創価学会の興亡(第一部)』を再刊して巻末に「隠し留められていた本門大本尊」という諫暁書を公刊しました。
第六回目として平成三年四月二十八日に、台湾台北市の本宗寺院で日蓮正宗信徒と私のあいだでおこなわれた問答の記録『台北問答』を発刊しました。
第七回目が平成三年九月十八日発行の『立正安世論Ⅰ』であります。そしてようやくこの時点で、なんとか、日蓮正宗総本山大石寺法主上人阿部日顕狙下の『大日蓮』誌上の、その量も五五ページにおよぶ大反論を引き出すことができたのも、大聖人の御仏智かと思います。
この「公場対決」は、阿部上人が放棄されない限り、決着をみるまで続けるつもりで、その量がまとまり次第、つぎつぎに公刊することをお約束して、あとがきに代えます。
なお本書収録の他の記事は、大部分本宗の宗報に発表されたものの再録です。
一九九一年十月二十日
(不思議にもこの日横浜市のはずれで、わが車の前を横切る一羽のオスのキジを目撃す)
玉井日禮
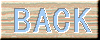
|