


 お 知 ら せ
お 知 ら せ 

 新サイトへアクセスの後、お気に入りの書き換えをよろしくお願いいたします。
新サイトへアクセスの後、お気に入りの書き換えをよろしくお願いいたします。
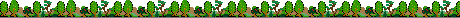
前垂れ式六尺褌の締め方をご説明しています。
 |
横廻しを縦廻しに引 っ掛ける準備です。 |
 |
縦廻しに横廻しを引 っ掛けたら、余りは 下から背中の皮膚の 側を通して上へ抜き ます。 |
 |
上へ抜いたところで す。 |
 |
適当に巻きます。し っかり巻きたい時は、 それなりの長さが必 要です。 |
 |
巻いている途中の後 ろの状態です。前垂 れ式では巻きは片側 だけですが、長さに余 裕があれば、両側に 巻くこともで可能です。 |
 |
余りを横廻しに巻き 終わった状態です。 余りの長さが十分あ る時には、左右に振 り分けて巻くこともで きます。 |
 |
終わりの巻きを左右 に振り分ける場合で す。写真のようにし ます。長さに余裕が ないとできません。 |
 |
片側を巻きます。こ の巻き方の場合、縦 廻しが多少浮き上が ります。 |
 |
片側の巻きを終わり、 反対側の巻きに入り ます。こちらは途中 で折り返して二重に なっていますので、 太くなります。 |
 |
両方を巻き終わりま した。片側だけ巻く のと比べますと、形 は整いますが、巻く のに面倒です。片側 だけ巻く方法で問題 ないと思います。 |
 |
前垂れ式褌を締め終 わりました。 |
 |
締め終わったところ を前から眺めたとこ ろです。 |
 |
褌の形が崩れた時は、 前垂れの上に巻いた 横廻しをたくし上げ、 形を整えます。 |
 |
前垂れの形や、締め 具合を直したら、また 元の様に戻します。 トイレの後等にはこ の様にして形を整え ます。 |
 |
前垂れ式のいいとこ ろは、ラフに締めて 楽しめるところです 。 |
 |
前垂れによって前袋 が見えません。これ によって、色気が醸 し出されます。 |
 |
後ろ姿です。巻きは 余り目立ちません。 |
 |
巻きを少なくしてあ りますので、すっき りした感じがします。 これで緩んだりはし ません。 |
 |
前袋式の六尺褌は緊 褌に締め、前垂れ式 六尺褌はゆったり締 めてお楽しみください。 |
 |
前袋式の六尺褌に慣 れたあなたも、是非前 垂れ式六尺褌も締め てみてください。新し い褌の世界が開けま す。 |
 |
浮世絵にあるような 前垂れは、どのよう に作るのでしょうか。 始めは三角形の場合 です。ほぼ幅の長さ を前へ垂らします 。 |
 |
前へ垂らした先の一 端をつまみ上げて、 三角形を作ります。 次に一番下の尖った 先を反対側の上へ持 っていきます。 |
 |
横廻しをたくし上げ ておき、反対側へ持 っていった前垂れで 今度は小さな三角形 を作り、それを横廻 しへ挟み込みます。 |
 |
挟み込んだ前垂れ の三角形の形を整 え、たくし上げた横 廻しを元の位置へ 戻して完成です。 |
 |
江戸時代の駕籠舁き がしているような前垂 れは、どのようにして 作るのでしょうか。 まず普通の六尺を締 めるように前垂れを 垂らします。 |
 |
前垂れの先端の片方 をつまみ上げ、前垂れ の中央部分の反対側 をつまんで、写真の ようにします。 |
 |
横廻しをたくし上げて おき、つまんだ前垂れ の真ん中を横へずら しながら、全体を水平 にして山を二つ作り、 横廻しへ挟み込み ます。 |
 |
形を整え、たくし上 げた横廻しを元へ 戻して完成です。 江戸時代の駕籠舁き らは、このようにして 前垂れ式褌を粋に締 めていたのです。 |
