(1888〜1963 ハンガリー →アメリカ)
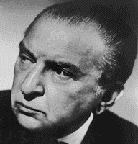
| えらーい人達 | |
| 九人目 フリッツ・ライナー ( REINER, Fritz ) (1888〜1963 ハンガリー →アメリカ) |
|
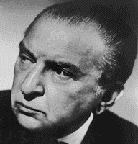 |
ハンガリーの首都ブダペストに生まれる。リスト音楽院で作曲とピアノを学ぶ。(この時の先生はバルトークの弟子でもある)また傍らでは一般大学で法律も修めている。「カルメン」で指揮者デビュー後、名門ドレスデン国立歌劇場の首席指揮者まで務めるのだが、その中で知り合ったリヒャルト・シュトラウスとはその後30年以上に渡る親交を結んでいる。ドレスデンを辞して以後しばらくして渡米。シンシナティ交響楽団のポストを得てアメリカを根拠とした活動を始める。その後1922年から10年余りカーティス音楽院で指揮を教えている。(この時の教え子に有名なレナード・バーンスタインがいる)シンシナティ以降はメトロポリタン歌劇場やピッツバーグ交響楽団等で活躍したが、1953年から亡くなるまでの10年間音楽監督を務めたシカゴ交響楽団を全米ナンバー1と言われるまでに鍛え上げた功績がつとに高名。非情なまでに精密無比な演奏が特徴。 |
|
一度見たら忘れられない指揮姿の人である。ずんぐりむっくりのかなり小柄な爺さんがじっと立っているだけという感じで、少々長めの棒の先っちょだけでビートを正確に刻んでいるのである。但し、その眼光だけは異様に鋭いもので、まさに一切を見抜いている眼そのものと言った感じだった。(これで睨まれる楽員はさぞかし恐かったことだろう) じっさいこの人は能力の低い楽員の首を切るので有名だったコワ〜イ指揮者の代表格だった。(この点ではトスカニーニ、セルと御三家)「ポケット・ビート」と揶揄された動きの極めて小さい指揮をシャレで双眼鏡で眺めた弦バスの楽員も次の日には首を切った程だから、要するにこの人にはシャレやギャグは無縁なのである。 演奏もまさにそうで、ライナーの録音を聴くと一切の妥協が無く、楽譜に書かれている音に対し完璧な再現を鬼の如く求める凄みさえが感じられる。(「指揮者の指揮者」と言われたのはダテではない)この人の録音で聴かれるライブ物とは明らかに異なる緊張感は恐らくこんな辺りから来ているのだろう。とにかくこの人の録音には好き嫌いはあっても駄作は無いと言って良い。僕にとって”プロフェッショナル”と言う言葉がライナーほどピッタリな人は他にそう見当たらない。 |
|
| ベートーヴェン:第5交響曲 | |
 ベートーヴェン I |
第1楽章から物凄い合奏が耳に飛び込んでくる。これほど見事な合奏はそう簡単にお目に掛かれるものではない。古楽器演奏真っ青な速めのテンポでグイグイと音楽を進めていく様は凄絶とさえ感じる。しかしよくもまぁこれほど上手い楽員達を集めたものだと思う。第3楽章の有名なチェロのパッセージなどを聴くとそれはまさに名手達の完璧な技である。(この頃のチェロ首席はその後ソリストで高名なヤーノシュ・シュタルケルである) ベートーヴェンの音楽に直球のみで勝負を挑んでいる姿にはただただ頭が下がる。演奏:シカゴ交響楽団 |
| バルトーク:管弦楽のための協奏曲、弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽 | |
 バルトーク : 管弦楽のための協奏曲&弦・打・チェレスタの音楽 |
バルトークが渡米する前と後の代表作2曲のカップリングの1枚。 演奏はハンガリー人のライナーだけあって本場マジャール気質が強い名演奏。しかし、それだけで終わらないのがライナーのライナーたる所以。もともとオケの各奏者に名人芸を要求するわ、ややこしいアンサンブルを仕掛けるわの何曲だけに、ライナーの締め上げは相当にきつかったのだろうか?ここで聴かれる鉄壁の合奏力は並ではない。こういう曲はこの様な完全無比の機能性を備えた演奏で聴くと余計に映える。 演奏:シカゴ交響楽団 |
| R・シュトラウス:交響詩「英雄の生涯」「ツァラトゥストラはこう語った」 | |
| もともとR・シュトラウスと親交のあった人だけに権威たる自信に満ちた名演。クールな音楽家であった作曲者とライナーには相通ずるものを感じてしまうのだが、ここで聴ける名曲2曲は例の如く鉄壁の合奏の中に漂う
”醒めた陶酔” が聴く耳を離さない。シュトラウスの音楽では聴き手は熱くなっても、演奏側は熱くなってはいけないように思う。そんな意味ではライナーの様な超一流の職人が手がけると素晴らしい結果になるような気がしてならない。 演奏:シカゴ交響楽団 |
|
|
|
|
| ライナーは今の感覚で捉えればいわゆる”暴君”と言っていい人で、現代に於いては絶対に存在し得ないタイプだ。しかし、この人のような超一流の職人に徹している人もいないのではなかろうか?彼ほど演奏の中に感情が入り込むことを否定した指揮者を僕は知らない。しかし、その徹底した作りで聴く合奏には頑としてびくともしない力強さが聴き手を捉えてしまう。今ではなんとなく地味な扱いをされているようだが、彼を知らないリスナーには是非お勧めしたい。もう一度書くが、向き不向きはあっても彼ほど駄作録音が無い人は珍しい。 | |