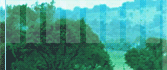|
|
|
|
 |
 庄内刺し子と遊佐刺し子の概要 庄内刺し子と遊佐刺し子の概要
土門 玲子
はじめに
庄内刺し子の発祥の地としての遊佐町は、古くは出羽国飽海都道佐郷の中心として栄え、
近くの酒田港は、北前船が停泊する地として発展し多くの荷物や人が行き交うところでも
あり文化の行き交う場所だった。
遊佐の名前は、延長5年(927年)縁起式兵部省に遊佐駅伝馬12ひきとあり、当時
馬継ぎ場として交通の要所で、そこに住まう人々もまた行き交う人からの文化を身に付け
て学んだと思われます。遊佐と言う地名が今現在も残っているのは日本全国にもめずらし
いことであり、他文化が入りやすい地域でもあったとおもわれます。それらの文化も今に
引き継がれ、その一つとして「刺し子」もあげられるのではないでしょうか。縫いとり刺
し子と言われる、ひたすら紋様を針目で絵柄を書くように現す刺し子と、遊佐町に現存す
る刺し子紋様との融合などもその一つではないかと思われます。
刺し子
刺し子は、素朴な着衣の繕いから、女達の知恵として生活の中で糸と針であみだされ手
から手と伝承されてきた技術である。農魚民は昔から古着を求めて作業着とし、この古着
に別布を重ねて綿糸により刺す事で薄くなりほころびはじめた洗いさらしの野良着を丈夫
にし、また布を幾枚も重ねて刺すことで厚く保温の良い着衣に仕上げたのである。
女連は着衣を丈夫に長持ちさせる目的だけでなく、直線に刺すことだけでなく斜め横等、
幾何学模様を形勢する楽しみを見いだし、模様により祝いの席に着る晴れ着としたり、嫁
入りの時には迎え人がきる法被などにも、女達が腕を競ったことが伺えるのです。
庄内刺し子と遊佐刺し子
庄内刺し子は遊佐刺し子、飛島刺しなど、庄内に一般的に広まった刺し子をひと
まとめにした名称である。
遊佐町には独特の刺し子が生み出され、長い年月にわたり保存伝承されてきた。一般的
に刺し子模様を刺す場合には、型紙を使用し模様を書きあらわしてから刺すが、遊佐町の
刺し方は型紙を必要とせず、糸の目数で模様を刺し現すのである。この刺し子手法を唯一
継承してきたのが遊佐町小原田の明治33年生まれ池田鉄恵さんであった。彼女の手法は
独特であり、昭和53年に保存のために遊佐町でも彼女を迎えて刺し子教室が開催される
などした。しかし近年は、目数のみで刺し子模様を現す技術は途絶え。その後の動きは型
紙を使用しての刺し子教室が現在も続けられている。昭和53年前後から庄内一円には高
橋閉代(とじよ)さんにより教授されて広まったとされる遊佐刺し子が見られ平田町の庄
内刺し子は高橋間代さん、堀千恵子さんにより教授され現在もなお発展している。遊佐刺
し子は特に、柿の花刺し・そろばん刺し・米刺し(米の字そのままを現す)など独特な物
が継承されている。刺し子は手から手と縫い継がれてきた事でその折々に刺す糸の針目の
状態で模様も創造されてきたと思われます。
参考資料 遊佐刺し子関係資料 菅原伝作氏
庄内刺し子を学ぶ婦人学級 村上良一氏
|
|
|
|
 |
|
|