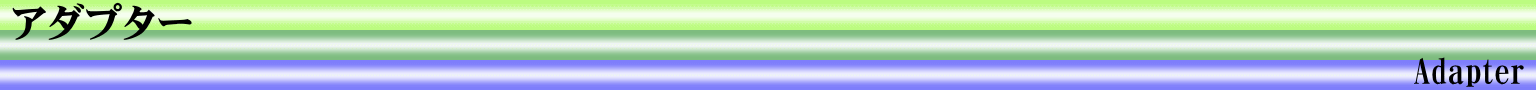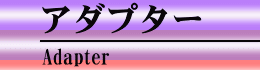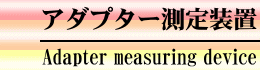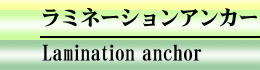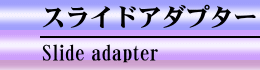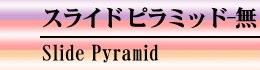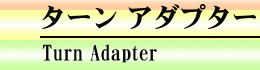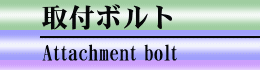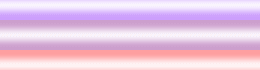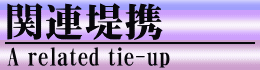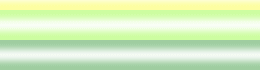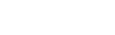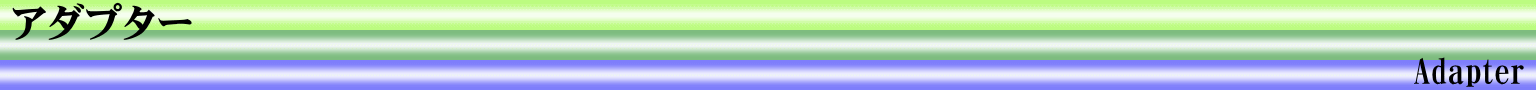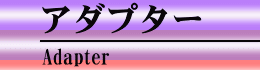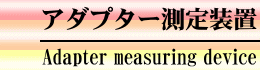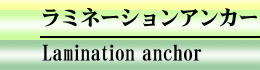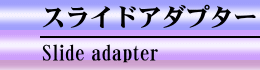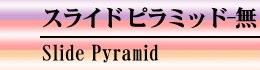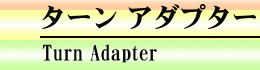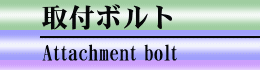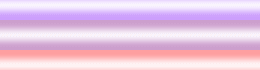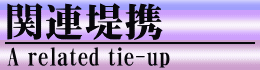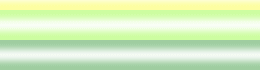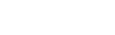従来の技術
【背景技術】
【0002】
従来から、例えば事故などで失った足の代わりとなる義足として、身体(切断脚の大腿断端部)に装着される上側構造部(ソケット部)と、この上側構造部に連結され下端部に接地部(足部)を有する下側構造部(下腿義肢部)とからなる義足(大腿義足)が提案されている。尚、この下側構造部には屈伸運動を可能にする膝関節として機能する屈伸部が設けられている。
【0003】
この上側構造部と下側構造部とは、図5に図示したように上側構造部31の下端部に設けた環状凹部31aに下側構造部32の上端部に設けた連結突部32aに螺着する構造である。
【0004】
ところで、上側構造部31が使用者の体型(骨格)に合わなかったり、身体へ装着した後、身体が成長により変形するなどして、身体に対して上側構造部31が最適でない装着状態(設計通りの角度でない装着状態)となった場合、歩行が良好に行えないという問題が生じる。これに対し、この上側構造部31を使用者に合うように予め専用設計すれば良いがコスト高となってしまい、仮に上側構造部31を専用設計したとしても、その後、身体が成長により変形するなどした場合には、やはり身体に対して上側構造部31が最適でない装着状態となり、良好な歩行が行えないという問題が生じてしまう。
【0005】
そこで、この問題を解決すべく、上側構造部51と下側構造部52の連結部に角度調整機能を具備せしめた義足(以下、従来例)が提案されている。
【0006】
この従来例は、図6に図示したように上側構造部51と下側構造部52との連結はリング部材55を介して行われる。具体的には、下側構造部52の上端部に設けた突状部53を上側構造部51に設けたリング部材55のリング孔55a内に配し、このリング部材55は、リング孔55a内に突出する挟持部材54(螺子部材)により突状部53を挟持するように構成されている。
【0007】
一方、上側構造部51に対するリング部材55の連結は、上側構造部51の下端部に設けた被嵌連結部56をリング部材55の上部に設けた連結突部55bに螺着することで行われる。
【0008】
つまり、従来例は、リング孔55a内で突出する挟持部材54夫々の突出量を可変して突状部53を挟持することで、上側構造部51を下側構造部52に対して水平状態若しくは適宜な傾斜状態で連結することができるものである。
【0009】
従って、従来例は、突状部53に対してリング部材55を最適な角度で配設すべく各挟持部材54を適宜な量だけ突出させて突状部53を挟持することで、上側構造部51に対して下側構造部52を身体に合った最適な状態で連結することができる。尚、身体へ装着した後、身体が成長するなどして変形したとしても、それに応じて突状部53に対してリング部材55を角度調整すれば良い。
|